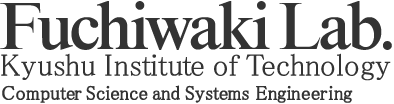早くも梅雨明けし,あまりの暑さにとろけてしまっている,D1の近藤です.紫陽花がちょうど見頃だった,6月13、14日に大分県の別府にて,せん断流の研究分科会がありました.この度は,その分科会に発表者として参加させていただきました.
分科会では,日本全国の大学および高専から教授がいらっしゃっており,自他の研究について活発な議論を行うことができました.普段の学会では,発表15min+質疑応答5minほどですが,今回の分科会では,発表30min+質疑応答10minだったため,普段より濃い議論ができました.参加させていただいて強く感じたことは,流体という学問の奥深さと,議論できる嬉しさです.私の他にも,発表者はお三方いらっしゃったのですが,同じ流体でも研究対象も手法も人それぞれで,いずれも新鮮な気持ちで拝聴しました.どの研究も大変興味深く,ノートに研究内容を書き留める手が止まりませんでした.また,すべての発表で質問および議論することができ,互いの考えや視点を語り合えることをとても嬉しく感じました.初めて聴く研究に対して,以前よりも要点をまとめてメモがとれるようになり,また,質問や議論ができるようになりました.このことから,今までゼミやポスター発表,シンポジウムなどで,様々な発表を聴いて,議論してきた経験が活きていると肌で感じることができました.これからも,様々な人と活発な議論ができるように,精進してまいります.
分科会の後には,流体を活用した技術見学として,ひょうたん温泉の竹製温泉冷却装置「湯雨竹」の説明を受けました.その装置は,竹枝を利用することで100℃の源泉を水滴状に分散させて,大気と触れる面積を増やし,47℃程度まで冷却するものでした.施設の方のご説明によると,昭和20年代から40年代ごろまで塩づくりに使われていた,流下式塩田の枝条架から着想を得ているとのことでした.流体力学が今ほど研究されていない時代に,この手法を生み出した古人の知恵に感動し,また,それが時を超え,形を変えて,現代に役立っている点に多大な感銘を受けました.私は熱いお湯に入ることができないのですが,今回,100%源泉かけ流しへの熱い思いに触れたことで,たとえどんなにお湯が熱くとも,水は断じて入れないと強く心に誓ったのでございます.
今回の分科会で様々な方と議論することができ,大変充実した時間でした.またお会いできたときに,より活発な議論ができるよう,もっと研究に邁進いたします.また,これから臆することなく様々な研究者に質問および議論をして,交流を広げたいと思いました.
ひょうたん温泉の見学風景 竹製温泉冷却温泉